【偏食】〝食べられる〟に変わる対応
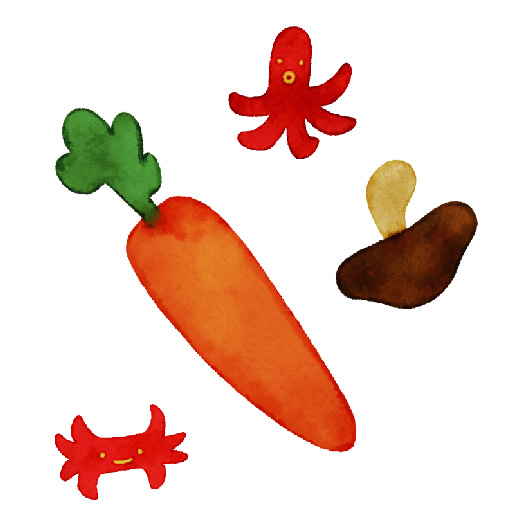 |
|
|---|---|
| 偏食は改善できるとよいですが、無理に対応すると子どもの負担に。何よりも〝食べられる〟ことを嬉しいと感じることが大切です。まずは、できる支援からスモールステップで進めていきましょう。 | |
| まずは、偏食の全体像の把握から 偏食のある子どもには、一人ひとり様々な特性、原因、環境があります。偏食の支援で重要なのは、食事のときだけの対応ではなく、どうしてその子が〝食べられない〟のか、様々な情報を得ながら、偏食にいたる理由を探ることです。 まずは保護者から子どもの様子を聞き取ることが必要です。療育機関や医療機関で相談している保護者もいるので、その話も丁寧に聞き取ると、園での対応もしやすくなります。偏食の理由は複数ある場合が多いです。子どもが何を嫌だと感じているのか、何に困っていて〝食べられない〟のかを知り、そのうえでの支援が〝食べられる〟へとつながります。また、苦手だった食材を〝食べた〟経験が、そのとき1回限りではなく、その後も続く状態が理想です。食べられたときは、何がその子にとってよかったのかを推測しながら、次につながるように記録していきましょう。 |
|
| 偏食対応の4つの柱 | |
| 1 情報収集 2 栄養管理 3 食事の支援 4 家庭との連携 保護者からの話の聞き取りと、その子が食べる様子を観察して情報収集。栄養管理に関しては、家庭での食生活も含めてのことなので、保護者と連携をとって情報交換を。園での食事の支援は、給食が自園調理であれば、栄養士や調理師にも協力を仰ぎましょう。 |
|
| 教えてくれた人/広島市西部こども療育センター 管理栄養士 藤井葉子 取材協力/太陽の子保育園(東京都) イラスト/たかはしけいこ 取材・文/仲尾匡代 |



