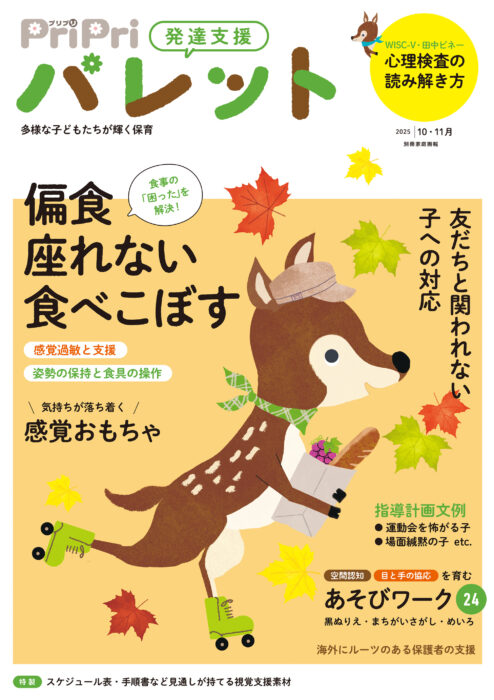ひとりでいることが多い子への対応①
 |
|
|---|---|
| ほかの子どもと関わらずひとりでいることが多い子どもがいると、保育者は、友だちとの関わりをつくってあげたいと思うのではないでしょうか?実際の園での支援をもとに、適切な対応を考えます。 | |
|
あそびの発達から考える子どもの友だち関係 子どもが友だちとなかよくあそぶ姿を願う保育者は多いでしょう。しかしひとりで過ごすことが心地よい子もおり、その子にとってはひとりで過ごす時間も大切です。 一般的な発達の子において、2~3歳頃は「並行あそび」の段階で、子ども同士が一緒にあそんでいるように見えても、直接的な交流はあまりありません。3~4歳頃になると、ほかの子どもと関わりながらあそぶ「連合あそび」に変化していきます。4~6歳頃では、目的を共有してあそぶ「協同あそび」へと発展し、簡単なルールのあるゲームなども楽しめるようになります。 一方で、発達に特性のある子どもは、一般的なあそびの発達の姿とは必ずしも一致せず、ときには友だちとの関わりを避けたり、集団でのあそびに苦手意識をもったりする場合があります。そのため、子どもがひとりでいたがるときは無理に集団に入れようとせず、反対に、友だちとの関わりを望んでいるときは、保育者が適切にサポートをしましょう。 |
|
|
なぜひとりでいるのか、その背景を考察する 発達に特性のある子どもがひとりで過ごす場面には、ことばの発達の遅れや社会的なスキルの未熟さから、コミュニケーションが難しいという背景があることもあります。また、興味の幅が狭かったりユニークすぎたりするために、友だちと共通の話題やあそびが見つかりにくいケースも。さらには、視覚や聴覚、触覚などに過敏さがあり、集団の場がストレスになっているケースも考えられます。 保育者は、子どもの特性をふまえ、ひとりでいる理由を推測して関わる必要があるでしょう。ひとりで過ごす時間も尊重しながら、その子のペースで友だちと関わる機会を増やせるように支援していくことが大切です。 |
|
|
あそびの発達と友だちとの関わり 友だちとの関わりは、あそびの発達とともに変化していきます。発達に特性のある子どもは、 一般的なあそびの発達とは必ずしも一致せず、異なる姿が見られる場合があります。 |
|
|
発達に特性のある子に
見られる姿 |
|
|
協同あそび (協同的な関わり) ●ほかの子と役割分担や、ルールを決めて、ひとつのあそびをする ●簡単なルールを理解し、友だちと協力する場面が増える ★コミュニケーションの難しさ(意図理解や相手の気持ちの理解、マイルールや興味の優先)から、誤解が生じることがある |
|
|
連合あそび (限定的な関わり) ●ほかの子と貸し借りなどをしながらあそぶ ●興味のあるあそびや活動を通じて、特定の友だちと関わることが増える ★ルールのあるあそびには苦手意識をもつことがある |
|
|
並行あそび (傍観者的な関わり) ●ほかの子の近くで同じあそびをするが、直接的な交流は少ない ●友だちの行動を観察し、真似する ★変化・変更に混乱しやすく、不安から参加を拒否したり、かんしゃくが増えたりする |
|
|
ひとりあそび (ひとりあそび中心) ●ほかの子どもの近くにはいるが、ひとりであそぶ ●友だちの存在を認識していても、積極的に関わることはあまりない ★パターン的な行動やこだわりが強くなる |
|
|
公認心理師、臨床発達心理士 白馬智美 イラスト/ナカムラチヒロ 取材・文/こんぺいとぷらねっと |