苦手さに配慮した
製作支援5 〜後編〜
 |
|
|---|---|
| 子どもの「やりたい」を引き出す支援を 発達に課題のある子は、手先が不器用だったり、感覚の過敏さによって材料にさわるのを嫌がったりする場合があります。そのため製作活動に不安を感じたり、集中力が持続しにくかったりすることも。保育者は、子ども一人ひとりの特性に合わせた支援を行うことが必要です。「苦手さに配慮した製作支援5〜前編〜」に続く「〜後編〜」を紹介します。 |
|
| ポイント3 写真や絵で視覚的に示す ことばで説明を聞くよりも、目から入る情報のほうが理解しやすい子がいます。写真や絵で視覚的に作り方の |
|
| ポイント4 認めることばで意欲を引き出す 小さなことでもできたことを一つひとつ認め、ほめましょう。成功体験を少しずつ積み重ねることで、「できた!」という達成感や子どもの自己肯定感が育まれ、活動へのモチベーションが上がります。 |
|
| ポイント5 自分で作った満足感をもてるように 保育者がすべてを手伝うと達成感が得られません。技法や材料を子どもに合ったものに変えることで、製作のスタート地点を変え、同じ仕上がりを目指せるように支援しましょう。 |
|
| ————————————————————– 教えてくれた人/武蔵野東第一・第二幼稚園特別支援教育コーディネーター 河井優子 制作/みさきゆい 写真/中島里小梨(世界文化ホールディングス) 取材・文/こんぺいとぷらねっと モデル/五条千衣 渡部葉月 |
|
この記事が詳しく掲載されているのは |
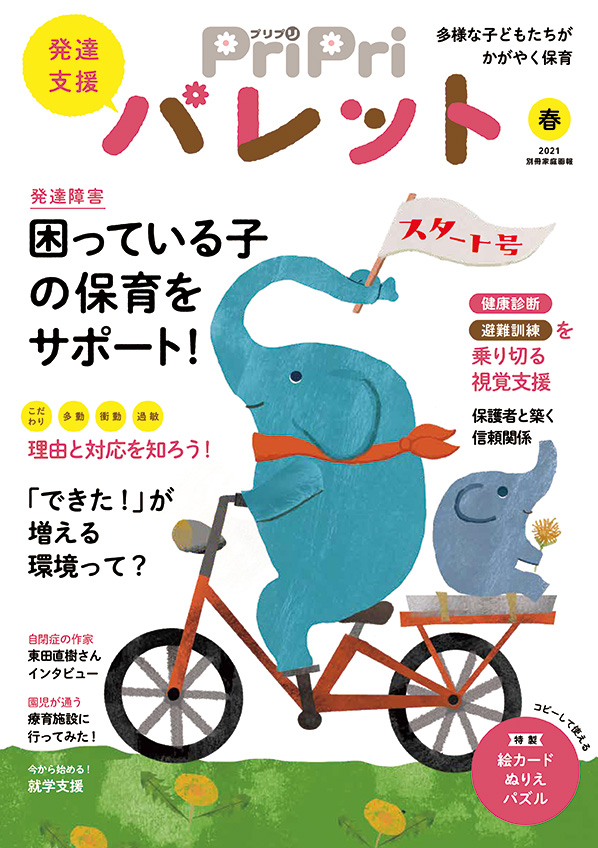 |
|
|---|---|
| PriPriパレット 春号 16ページに掲載 |
