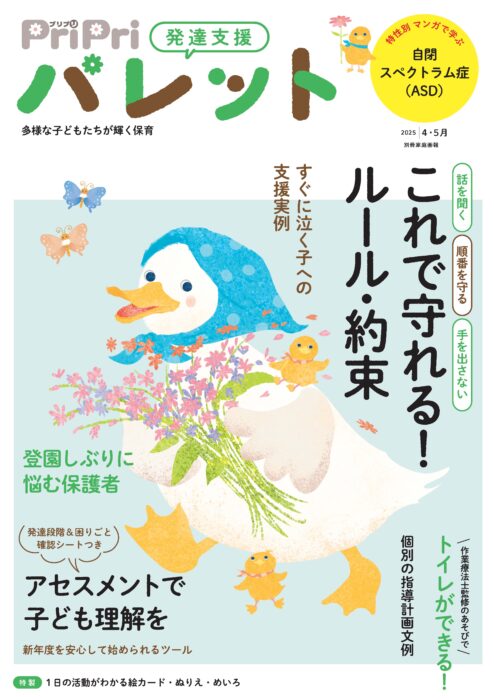その子の困りごと、どこに理由があるの?
 |
|
|---|---|
| 車いすの子の登園場面と、製作をしている子の保育室での場面、どこに問題があると思いますか? 一緒に考えてみましょう。 | |
|
車いすの子が園に入れない理由は ・スロープがない ・エレベーターがない |
|
|
この考え方は 社会モデル 困難の原因が、障害者の存在を想定していない社会側にあるとする考え方。障害の有無に関わらず、全ての人々が問題なく生活できるように、社会が変わることが必要とされます。この場合は、段差があることが困難の原因に。 |
|
|
困難の理由は社会の側にある 障害のある人が直面する困難は、障害そのものが原因なのか、それとも社会や環境によるものなのか。その捉え方によって、困難へのアプローチが変わります。 現代社会は障害のない多くの人(=マジョリティー)が暮らしやすいようにつくられています。ですが、誰もが安心して過ごせるインクルーシブな社会にするには、少数派の人(=マイノリティー)がいることを前提とした環境づくりが必須に。困難は、個人が努力や我慢で乗り越えるものではなく、社会側の変革でなくすべきものです。 |
|
|
多動傾向のある子が製作活動に参加できない理由は ・注意力が弱い ・衝動性がある |
|
|
この考え方は 医学モデル 生活上に困難が生じた際、困難の原因が個人の障害そのものにあるとする考え方。その困難をなくすには、障害の治療や、訓練などによる改善が必要とされます。この場合は注意欠如・多動症(ADHD)の特性が困難の原因とされます。 |
|
|
どの子にとっても活動しやすい環境を 上図の子の気の散りやすさは、注意欠如・多動症(ADHD)の特性に由来しますが、こうした姿は程度は違えど、定型発達児にも見られます。例えば読み聞かせの際、掲示物がごちゃごちゃ貼られた壁が背景では誰もが気が散りやすく、白壁の背景の方が集中しやすくなります。活動を説明する際も、長い文章ではなく、短い文章でイラストを交えて話す方が、伝わりやすくなります。困りごとの原因はその子の外側(=環境)にあり、それを変えれば誰もが活動しやすくなるのです。 |
|
|
社会モデルの視点で見えてくる障壁 ・掲示物が多い ・ひとつの活動が長すぎる ・席が遠く保育者の声が耳に入らない ・製作物が子どもの興味に即していない |
|
|
困りごとの原因は“社会”の側に。 多様な人たちを前提に変える、 インクルーシブな社会へ |
|
|
教えてくれた人/ インクルージョン研究者・一般社団法人UNIVA理事 野口晃菜 イラスト/イオクサツキ 取材・文/仲尾匡代 |