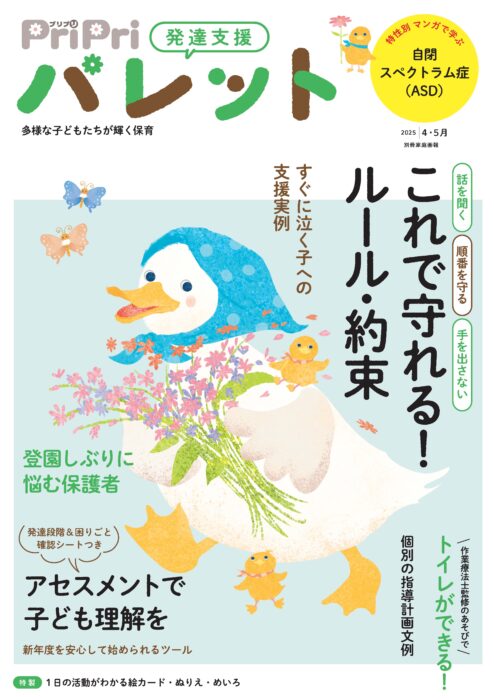「すぐに泣いてしまう子」への対応①
 |
|
|---|---|
| ちょっとしたことで泣き出し、なかなか気持ちを立て直せない子どもや、グズグズといつまでも泣き続ける子がいます。どう対応してよいか、迷う場面もあるのではないでしょうか? 園での事例をもとに、適切な支援のあり方を考えます。 | |
|
泣く行為にも発達上の意味がある 子どもにとって、泣く行為には大切な意味があります。まだことばを十分に使えない子どもは、泣く行為がコミュニケーションのひとつであり、空腹や疲れ、痛み、不快感などを周囲の大人に伝える手段となります。泣いて周囲の注意をひき、対応を得るのです。 もちろん、感情表現として泣く場合もあります。泣いて、喜び、悲しみ、怒りなどの感情を表し、気持ちを整理して、心の健康を保ちます。 このように、子どもにとって泣く行為には大切な役割がありますが、成長するにつれてことばでのやり取りができるようになると、泣くだけに頼らないコミュニケーションができるようになっていきます。 |
|
|
泣く行為以外の手段を学ぶ 発達に特性のある子は、ことばや理解の遅れ、コミュニケーション手段の少なさや、予測不能な状況への不安感から、強いストレスを受けている場合があります。感覚過敏があると、些細な刺激でも不快に感じる場合もあります。また、思い通りにできないことや失敗を気にしすぎて、かんしゃくを起こしたり、感情のコントロールができず、すぐに泣いてしまう子がいます。 泣くこと自体は、周囲に助けを求める大切なサインでもあるので、無理に止める必要はありません。しかし、原因を探ることは大切です。そのうえで、泣きたい気持ちや不安に寄り添いながら子どもの気持ちをことばで代弁し、少しずつ自分で気持ちを調整できるように支援していきましょう。 また、子どもが自分でできることとサポートが必要なことを整理したり、クールダウンできる場所を確保するといった環境の調整も大切です。小さな成功体験を認めながら、自尊心を育めるように関わっていきましょう。 |
|
|
すぐに泣いてしまう子の背景 ・コミュニケーションの手段が少ない ・見通しがもてないため不安が強い ・感情コントロールが苦手 ・生活リズムの乱れで安定しない |
|
|
ちょっとしたことで泣き出し、その場で立ち尽くすAさん お気に入りのおもちゃが見つからないといった、一見すると些細なことで泣き出し、保育者が来るまで動けずにいる3歳のAさん。発達がゆっくりで、ことばで気持ちを伝えることはまだ難しい状態です。 |
|
|
「わかってできる」をサポート Aさんにとって保育室は、友だちの声や動き、一斉指示の説明など、情報が多すぎてわかりにくく、不安を感じる場所になっていました。そこで、ロッカーに手順表を貼り、朝の支度を1か所で完結できるようにしました。また、隣の子との間に衝立を置き、自分の場所をわかりやすくしました。すると、「わかってできた!」と自信をもって取り組めることが増えました。 |
|
|
少し離れた場所から声をかける 泣き出したら少し離れた場所に待機して、保育者の近くに来るように促しました。そのうえで、友だちとの場面では、子どもの気持ちを代弁しながら「貸して」「ちょうだい」「手伝って」などと一緒に言うようにし、振る舞い方の手本を見せています。 |
|
|
つまずきやすい場面ときっかけをまずは観察してみる どのような場面やきっかけで泣き出すのかをよく観察して、何日間か記録をとってみましょう。時間帯や場面、体調などの関連性が見えてくるかもしれません。自分でできることとサポートが必要な場面を整理して、できることを増やしながら、自己肯定感を高められるように支援していきましょう。 泣いたらすぐに保育者が来てくれるので、泣けば要求が通ると学んでいる可能性もあります。保育者は少し離れた場所から見守り、子どもから保育者に伝えに来るようにしてみましょう。 |
|
|
公認心理師、臨床発達心理士 白馬智美 イラスト/ナカムラチヒロ 取材・文/こんぺいとぷらねっと |