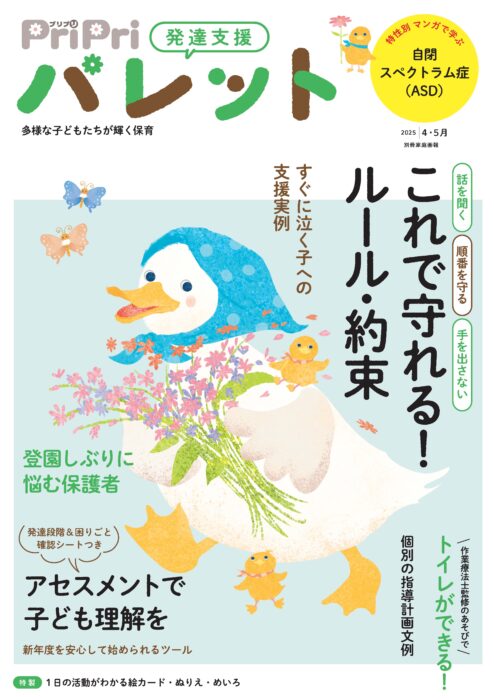“はまる支援”が見えてくるアセスメント力を高めよう①
 |
|
|---|---|
| 保育の分野でも聞かれるようになり、注目度が増してきた「アセスメント」。その目的やメリット、支援につながる活用法などについて解説します。アセスメントの力を高めて、子どもの支援に生かしましょう。 | |
|
\アセスメントとは/ アセスメントとは、本来「評価」「査定」を意味することば。介護、医療、教育などの分野では対象となる人を客観的に評価・分析し、解決すべき課題に適切に対応するために行います。 |
|
|
アセスメントで深まる子どもへの理解 アセスメントとは、もともと「評価・査定」を意味する英語の「assessment」から生まれたことば。病院や介護施設などでは、患者や利用者のニーズに即した看護計画、あるいは介護計画を作成するために、アセスメントはなくてはならない重要な業務のひとつです。保育におけるアセスメントも同様、その目的は、子どもの発達段階や課題などを把握し、必要な支援を明確化すること。子どもの発達や特性を客観的に評価・分析し、子どもへの理解を深めるアセスメントは、発達に課題のある子の支援をよりよくするための有効なプロセスだといえます。 |
|
|
アセスメントで子どもが育つ、保育が変わる! |
|
|
支援の根幹は、子どもの状態像を捉えること 「どんな支援をすればよいかわからない」「支援がうまくいかない」など、発達に課題のある子への支援に悩みや戸惑いを感じている保育者は少なくないでしょう。 よい支援を行うには、支援の引き出し、ノウハウをたくさん持っていることも必要な要素のひとつです。しかしそれ以前に大切なのは、「どれだけ子どもの状態像を捉えているか」ということ。〝状態像〟とは、目の前にいる子どもの姿や発達を意味し、それらを捉えることは、まさに保育の核となる「子ども理解」に通じます。支援のノウハウがあっても、「その子が必要とする支援、その子に合った支援」に合致していなければ、支援の効果は望めません。 |
|
|
アセスメントが保育にもたらす好循環 そこで必要になるのがアセスメントです。アセスメントで子どもの状態像を捉えられると、その子が今、必要とする支援(=適切な支援)が見えてきます。 発達に課題のある子は、集団生活のなかで後れをとったり、注意を受けたりすることが多くなりがちですが、適切な支援があればできることが増え、失敗体験は少なくなります。幼少期から成功体験を積み重ねて自己肯定感を育むことは、将来、子どもが人生をよりよく歩んでいくためにもとても大切です。また、適切な支援で子どもに目に見える成長があれば、保育者も支援の手応えを感じられるでしょう。そして、アセスメントの内容と支援による変化を保護者と共有しておけば、保護者も子育てのモチベーションを上げられます。アセスメントによって適切な支援を行うことで、子どもをとりまく環境によい循環が生まれるという効果があります。 |
|
|
教えてくれた人/安部 博志 イラスト/Aikoberry 取材・文/森 麻子 |