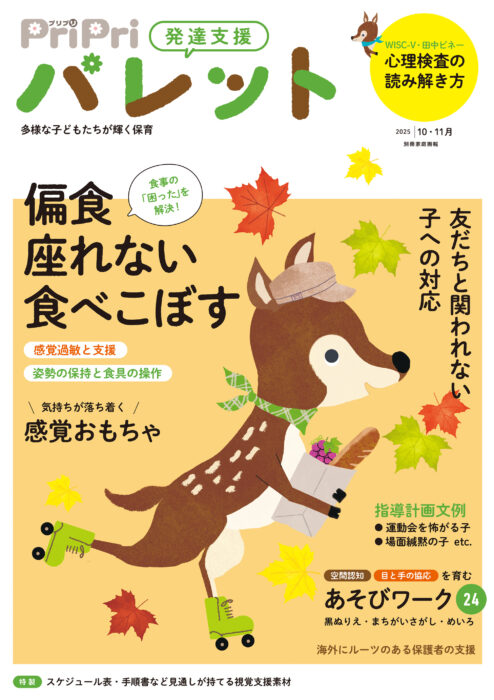偏食の子への対応④
 |
|
|---|---|
|
\チェックシートつき/ 偏食支援は状況把握が大切 日々の食事や生活で、その子が〝食べられない〟理由を探し、それに合わせた支援を試みましょう。偏食の改善により、子ども自身が〝食べられる〟ことを嬉しいと感じるようになることが大切です。 |
|
|
偏食の全体像を、保護者とともに確認を 偏食の支援で大切なのは、園で食事をする際の対応だけではなく、その子がなぜ〝食べられない〟のか、様々な情報を得て偏食の理由を探ることです。そのためには、その子の偏食の全体像を把握することが最も重要となります。 まずは保護者から子どもの様子を聞き取ることから始めましょう。その際、保護者の気持ちに寄り添い、共に子どもの幸せを願って協力し合う関係となる対応を心がけましょう。 偏食支援では、苦手だった食材を支援によって食べられるようになるだけではなく、特別な支援がなくても、食べられるようになることが理想です。また、家庭での対応が改善の要になることを、保護者に理解してもらうことも大切です。就学後も視野に入れ、園と家庭で密にコミュニケーションを取り、連携しながら進めていけるとよいでしょう。 |
|
|
保護者への聞き取り 情報が多いほど子どもの状態をより正確に把握でき、対応の幅も広がります。基本的な身体情報、生活リズム、好き嫌い、家庭での食事内容や食事時の環境や様子など、現時点の情報のほかに、成育歴や、保護者の今までの苦労や工夫なども聞いておくとよいでしょう。 聞き取りポイント● 身長/体重 ● 障害/疾患 ● 成育歴 ● 発達状況(言語理解・認知など) ● 朝食・昼食・夕食の内容 ● 食事以外のおやつ、飲料等 etc. |
|
|
身体・栄養 偏食が体の発達にどう影響しているかの確認も大切です。成長曲線やカウプ指数をチェックし、家庭で食べているものの品目や摂取量の記録と見比べると、食べ方のバランスや栄養状態がわかります。食事時間以外に菓子やジュースなど好きなものばかり摂取していると、それだけでおなかがいっぱいになり、ほかのものが食べられず栄養も偏ります。栄養士がいる場合は協力を仰ぎましょう。 ※カウプ指数は体重(㎏)÷身長(m)÷ 身長(m)で算出。一般的に3~5歳は14.5~16.5が平均的な数値ですが、16以下であった方が偏食が改善しやすい傾向があります。 |
|
|
口腔機能の状態を確認 噛んですりつぶさないと飲み込めない食材は食べず、とろみのあるメニューや軟らかくて飲み込める食材ばかり食べているなら、噛めていないのかも。ご飯を噛まずに飲み込んでいる子もいます。あごを上下にしっかり動かし奥歯で噛めているか、食材をすりつぶせているかなど、食べる様子の確認を。噛む力がつくと、偏食が改善されやすくなります。 |
|
|
教えてくれた人/ 管理栄養士 藤井葉子 イラスト/たにざきまほ 撮影/五十嵐 公 磯﨑威志(Focus & Graph Studio) 中島里小梨(世界文化ホールディングス) 取材・文/仲尾匡代(P.4〜13) |