特定のものしか食べられない偏食~背景~
| 食べられるものが限定的な「偏食」は、「わがまま」ではなく、身を守るための「行動」。偏食の背景には、どのような特性があるのでしょうか。 | |
|---|---|
 |
|
| 偏食の背景にある特性 | |
| こだわりが強い 興味や関心の幅が狭いことから、「ごはんは白いもの」などといったマイルールにとらわれ、食べたことのない食べ物に不安を感じる |
|
| 家と異なる状態への不安 変化を嫌がるため、家で食べられても園では同じ食べ物と判断ができず、不安になる |
|
| 感覚が過敏 触覚、味覚、視覚、聴覚、嗅覚に過敏さがあるため、「揚げ物の衣が口にささる!」などの不快を感じる |
|
| 食の豊富な現代、食べられるものがすこしでもあれば、まずは安心を。成長曲線から大きく外れている、カロリーが足りず風邪をひきやすいといったことがなければ大丈夫です。「完食」にとらわれず、食べられるものが増えたら、食事が楽しく、ラクになるというくらいのおおらかな気持ちで、子どもと向き合ってみましょう。 とはいえ、食の困難は日々の切実な悩み。保育者は、保護者への聞き取りを交え、子どもの様子をよく観察しましょう。何を食べなかったではなく、何を、どんな状況で、どう食べたのか。食事のパターンがわかったら、その子にあわせた「食べられる」調理法や環境を作ります。食べねばならない、食べさせねばならないでは、子どもも保育者も互いに辛くなってしまうだけ。子どもにとって保育者を安心できる人、園を安心できる環境にできれば、「先生が、園が、出したものなら大丈夫」と、食べられるものが増えていきます。ふだんの保育から信頼関係を築くことをはじめの一歩にしましょう。 |
|
| 「特定のものしか食べられない偏食~対応~」は7月2日公開予定。 | |
| ————————————————————– 教えてくれた人 |
|
| 帆足暁子 公認心理士、臨床心理士。保育士、幼稚園教諭の資格も持ち、保育や子育て相談を通して子どもと向き合う。現在は「親と子どもの臨床支援センター」(東京都三鷹市)代表理事、東京家政大学非常勤講師。 |
|
この記事が詳しく掲載されているのは |
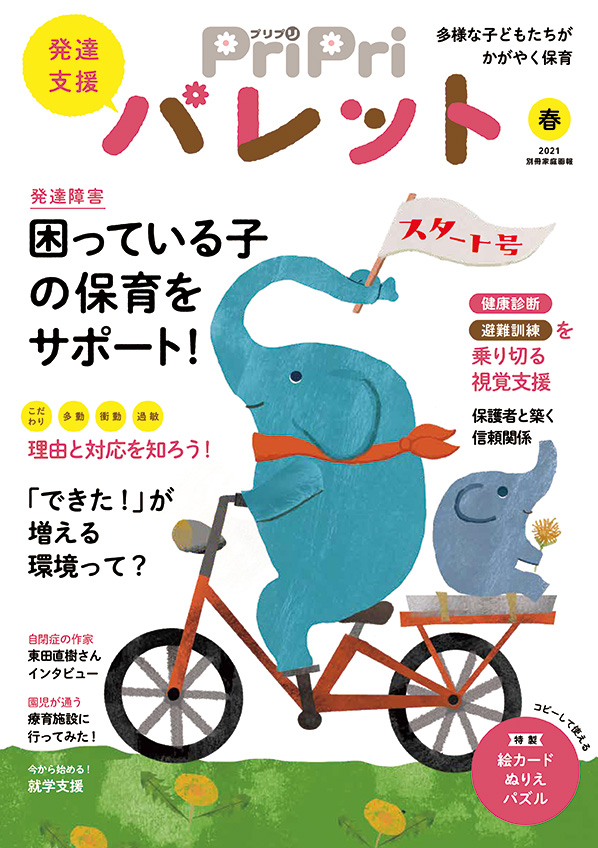 |
|
|---|---|
| PriPriパレット 春号 71ページに掲載 |
