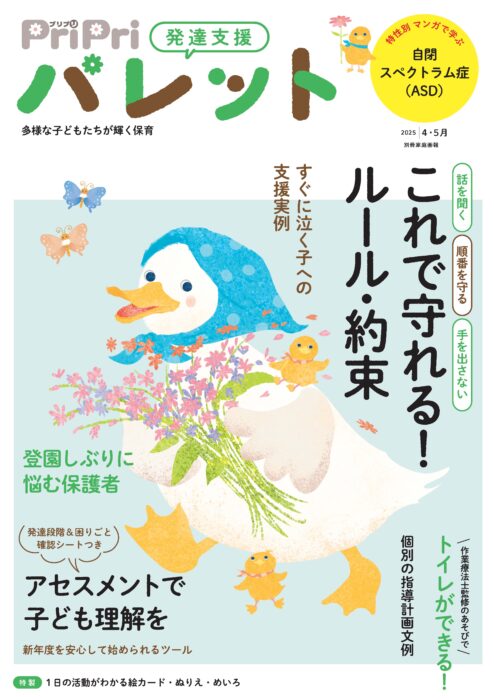行動のワケを知りたい、関わりたい自閉スペクトラム症①
 |
|
|---|---|
| ASDと略されることもある自閉スペクトラム症。障害名を知ってはいるけれど、どんな特性があり、その子にどう関わるのがよいのか、わからず戸惑う保育者もいるでしょう。特性と望ましい関わり方について、事例を交えて解説します。 | |
|
自閉スペクトラム症には多様なタイプが 自閉スペクトラム症という診断名は、2013年から一般的に使用されるようになりました。以前は、「自閉症」「アスペルガー症候群」「高機能自閉症」「広汎性発達障害」など、知的障害の有無や特性の表れ方によって診断名が細分化されていました。これらすべての診断名をまとめたのが、自閉スペクトラム症(以下ASDと表記)です。 ASDの特性は様々あり、特性の表れ方はその子によって異なります。そのため、抱えている困難も一人ひとり違います。自閉スペクトラム症の「スペクトラム」は、境界線のない連続した状態を示していますが「スペクトラムを〝多様性〟と捉える考え方もあるかもしれません。ASDの特性は定型発達児にも無縁ではなく、こだわりや感覚過敏のある子もいます。支援が必要かどうかの線引きは、特性による生きづらさがあるかどうかが、重要なポイントになります。 |
|
|
ほかの発達障害やてんかんとの併存も ASDの特性の表れ方は一人ひとり異なりますが、表れ方の違いには、ほかの発達障害が関係している場合も。注意欠如・多動症(ADHD)や学習障害(LD)といった発達障害の併存や、脳の神経疾患であるてんかんの併存も多く見られます。 ASDというという診断名は支援の参考にできますが、その診断名は同じとて、誰に対しても決まった対応がある訳ではありません。その子自身が何に困っているのかを見極め、個別に対応しましょう。 |
|
|
幼児期の関わりで大切にしたい3か条 |
|
|
その子らしさを受け入れることから 意図や気持ちを想像しにくい行動や振る舞いがあるかもしれませんが、それを矯正しようとせず、まずはその子のあるがままを受け入れましょう。その子の特性はその子らしさ、一人ひとり違った個性のひとつと捉えます。子どもの意に反することを強制すると、不安やストレスが生じ、パニックを起こす要因にも。その子が園で楽しく過ごせることを優先しましょう。 |
|
|
自己肯定感を高め、二次障害を予防 ASDの特性により、友だちとトラブルを起こしてしまう場合もあります。しかし、叱られたり非難されたりすることが続くと「自分はダメな子だ」と自分を責めるようにも。すると人との関わりを拒む、体に不調が出る、問題行動を起こすなどの二次障害も。苦手を克服させようとするのではなく、得意を伸ばすような心がけを。二次障害を予防できるよう、その子が過ごしやすい環境を整えることが大切です。 |
|
|
1 興味や感覚特性を理解し、共感的に接する 個々の特有の興味や感覚の特性を理解し、受け入れる。 |
|
|
2 安定した環境を、保つことを重視する 日々の生活リズムや環境を安定させ、活動のルーティンをつくる。 |
|
|
3 社会的スキルやコミュニケーション能力を無理なく育む 円滑な人間関係における知識や技術などを、無理のない範囲で伝える。 |
|
|
教えてくれた人/ チャイルドフッド·ラボ代表理事 藤原里美 イラスト/オガワナホ 取材・文/仲尾匡代 |