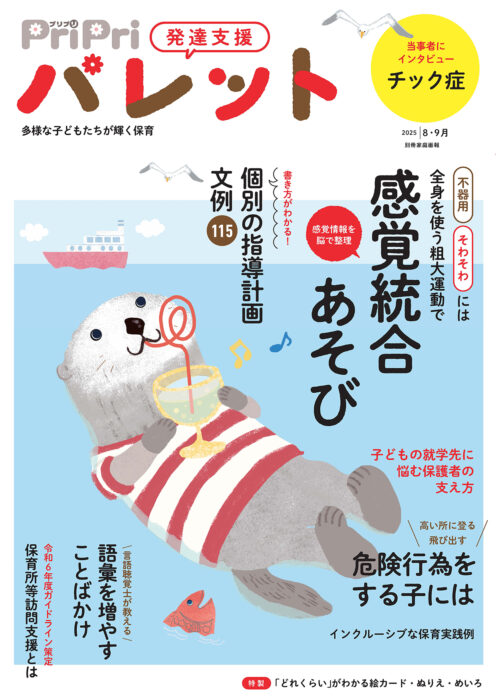子どもの就学に悩む保護者対応②
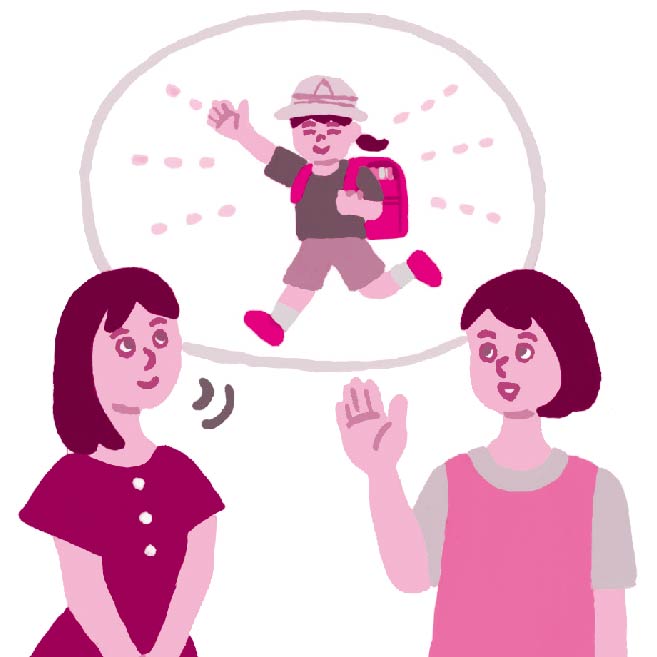 |
|
|---|---|
| 発達に特性のある子どもの保護者とのやりとりは、思いに寄り添った接し方が大切です。様々なケースを取り上げて、よい関係を築く対応をご紹介します。 | |
|
ケーススタディ
|
|
|
大丈夫と言ってもらいたい? 「通常の学級で大丈夫ですよね」と何度も聞かれる 「先生、うちの子は通常の学級で大丈夫ですよね?」と何度も聞いてくる保護者がいます。保護者としては、就学後の子どもが心配で、何か気になることがあるようなのですが、返答に困ってしまいました。どう答えたらよいでしょうか。 |
|
|
こう対応! その子の今の姿を共有し、就学への不安を受け止める 保護者には、保育者に大丈夫と言ってもらいたい気持ちと、心配な気持ちがあるのでしょう。こういう場合は「大丈夫じゃないですか」などと当たり障りのない返事はせず、具体的に心配な点を聞き、保護者の不安に寄り添う対応が大切です。園での子どもの様子や、保育者の支援があればうまくできる姿などを保護者と共有するとともに、通常の学級でもその子に合った支援を受けられること、就学後にも在籍学級や学校の変更を相談できることを伝えましょう。 |
|
 |
|
|
就学相談を勧めたいけれど 就学相談は我が子には関係ないと思っている保護者 こだわりが強く、友だちとうまく関われなくてよくトラブルになる子がいます。就学後が心配なので、就学相談を受けるとよいのではないかと思い、保護者にそれとなく話してみましたが聞く耳を持ってくれません。どう対応したらよいでしょうか。 |
|
|
こう対応! 無理強いせず、困った時に相談できる関係づくりを 「うちの子に就学相談は関係ない」と考えている保護者に、保育者が無理に就学相談を勧めるのは控えましょう。「うちの子には必要ないと言っているのに、あの先生は何度も言ってくる」などと、保育者に対して不信感が湧き、信頼関係が崩れてしまう場合もあります。保育者はいつも通りに保育のなかで子どもを支援し、保護者が今後困ったり悩んだりした時に相談しやすい関係を築いておくことが大切です。 |
|
 |
|
|
就学相談に行ったところ…… 特別支援学級を提案されてショックを受けた保護者 発達に特性がある子とその保護者が、就学相談に行ったところ、特別支援学級がよいのではと提案を受けたそうです。その結果に保護者がショックを受けたようで、送迎時の口数が少なくなってしまいました。どのように支えたらよいでしょうか。 |
|
|
こう対応! その子に合った支援と環境が子どもを輝かせることを伝えて 精神的に落ち込んでいる保護者の気持ちを受け止め、話せるようになるまでは優しく見守りましょう。気持ちが落ち着いたら、特別支援学級に就学した卒園生の様子を、差し支えない範囲で伝えてみるのもよいでしょう。就学後に適切な支援を受け、安心できる環境でいきいきと過ごしている子がいることを知り、前向きに捉えられるようになることも。同時に「卒園後もいつでも園に相談しにきてください」などと伝え、不安が軽くなるように寄り添いましょう。 |
|
|
<知っておきたい> 就学先には4つの選択肢が 公立校の場合、以下の4つの就学先があります。障害の診断の有無にかかわらず、知的面、情緒面、身体の発達等の状態に応じ、就学相談にて教育、医療、心理などの専門家とともに検討します。 通常の学級 一般的な集団の学級で、1クラス35人以下の集団授業が基本。必要に応じて合理的配慮がなされる。 通級による指導 通常の学級に在籍し、週に数単位時間、別教室でその子の特性のニーズにあった個別の指導が受けられる。 特別支援学級 個別のニーズに合った教育を目的とした1クラス8人以下の学級。対象となる障害は自閉症・情緒障害、知的障害、肢体不自由、難聴、弱視、言語障害、病弱及び身体虚弱など。通常学級との交流及び共同学習も。 特別支援学校小学部 障害の程度が比較的重い子どもを対象として、各教科に加え、自立を促すために必要な指導を一人ひとりの障害や発達に応じた形で受けられる。対象となる障害は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱など。 |
|
|
<FROM 徳田先生> 「子どもにとってよい環境を」という視点がぶれないように 就学に悩む保護者の気持ちは日々揺れています。大切なのは「子どものために就学先を決める」と心に決めて考えること。保育者は園での子どもの姿を伝えながら、保護者の不安に寄り添い、しっかり支えていきましょう。 |
|
|
教えてくれた人/ 筑波大学名誉教授 徳田克己 東京科学大学 リベラルアーツ研究教育院教授 水野智美 イラスト/コウゼンアヤコ 取材・文/小栗亜希子 |