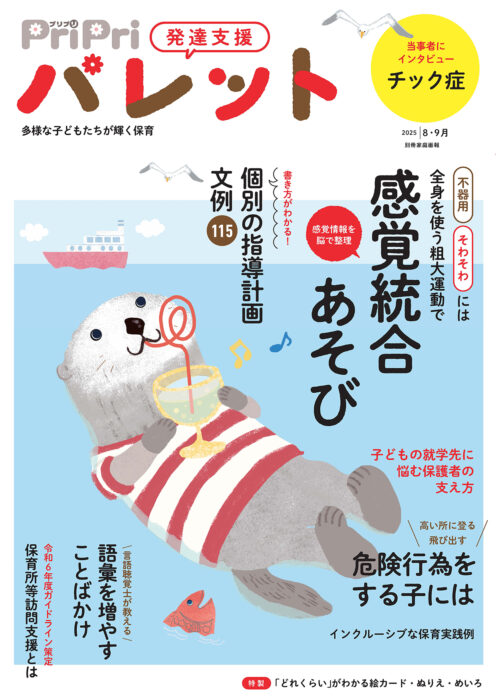「マジョリティー中心」になっていない?
 |
|
|---|---|
| 社会における制度や文化は、多数派を中心につくられています。「これまで通りの保育」は、少数派に不便や困難を強いている場合も。園でそのようなことがないか、見直してみましょう。 | |
|
駅の改札やはさみ、左利きの人が困るのは? ・それらが、右利きの人向けに作られているから |
|
|
原因となるのは 構造的差別 社会のなかに埋め込まれている、一定の属性を持つグループが不利益を被ったり差別を受けたりする社会制度や慣習を指します。対象となる属性は、女性、外国人、障害者、貧困者、性的マイノリティーなど多岐にわたります。 |
|
|
多勢に合わせようと、我慢をさせていない? インクルーシブな社会の実現には、現代社会が多勢となるマジョリティーに都合よくつくられていると気づく姿勢が大切です。例えば自分の足でどこへでも行けることは身体的マジョリティーの特権で、車いすの人はマイノリティーにあたり、一日三食食べられるのは経済的マジョリティーの特権です。 改札は右利きの人を想定して作られており、左利きの人はICカードのタッチに不便を感じます。はさみも刃の合わせが右利きの人を想定しており、左利きの人は作業が困難に。多数派向けに作られているものは、少数派の人には不都合が生じやすく我慢を強いられがちです。ここで言う「マジョリティー」とは数の多さのみならず「より権力がある」「より意思決定しやすい」立場を指します。例えば男女だと男性がマジョリティー。男性優位の社会では、数では同等の女性が不利となることも多いのです。命の危険に関わる例では、車のシートベルトがあげられます。主に男性向けに作られているため、交通事故の重傷率は女性の方が高いと言われます。 |
|
|
運動会や発表会が苦手なのは? ・大きな音が苦手だから・照明がまぶしくて目が開けられないから ・いつもと違う環境で不安になるからetc. |
|
|
必要なのは 環境の改善 困っている子に、つらさを感じていないほかの子たちと同じように行事に参加させようと個別の支援をするよりも、誰もが参加できる行事にすることを考えましょう。演目内容に加え、環境の改善が重要です。 |
|
|
子どもの多様性に合わせた行事を 園生活においても、運動会や発表会などの行事は特にマジョリティー優先となりがちです。障害の有無や国籍に関わらず、苦手な演目や活動を強いられている子はいないでしょうか? その子に無理をさせて多勢に合わせようとすることは、個別の支援があったとしてもインクルーシブな保育とはいえません。誰もが楽しく参加するにはどうしたらよいのか、行事そのものの在り方や内容を保育者間で話し合ってみましょう。 |
|
|
教えてくれた人/ インクルージョン研究者・一般社団法人UNIVA理事 野口晃菜 取材協力/四季の森幼稚園(神奈川県) イラスト/オオイシチエ 取材・文/仲尾匡代 |